そもそも打撲ってなに?
打撲(だぼく)とは、体の一部を強くぶつけたり、衝突したりすることで起こる外傷のことです。
交通事故では、加害者の車や自転車などが体にぶつかって、打撲を起こすことがありますし、車を運転中に玉突き事故を起こされて、その衝撃で車内のハンドルなどに体をぶつけて、打撲を起こすこともあります。
皮膚の表面には目立った傷がないにもかかわらず、その下の筋肉や血管、皮下組織が損傷を受け、内出血や腫れ、痛みを引き起こします。
打撲・挫傷・血腫の違い
「打撲」「挫傷」「血腫」
これらの言葉、似ているようで実はそれぞれ異なる意味を持っています。打撲と混同されやすいこれらの状態について、その違いを分かりやすく解説します。
1. 打撲(だぼく)
定義: 身体をぶつけたり、打たれたりして、主に皮膚や皮下組織、筋肉などが損傷を受けた状態を指します。「打ち身」とも呼ばれます。皮膚の表面に傷(切り傷など)はないものの、内部の組織がダメージを受けています。
症状: 痛み、腫れ、熱感、内出血(青あざ)などが典型的です。青紫色の内出血は、時間が経つと黄色に変色して、次第に消えていきます。
特徴: 比較的一般的な怪我で、軽度であれば自然に治癒することが多いですが、重度の場合、骨折や内臓損傷を伴う可能性があるので注意が必要です。
2. 挫傷(ざしょう)
定義: 鈍的な力(打撃や圧迫など)によって、体内の組織や臓器が損傷した状態を指します。広義では打撲も挫傷の一種と捉えられます。皮膚の表面に傷がない場合が多く、内部の軟部組織(筋肉、靭帯、血管など)が損傷の主体となります。
症状: 打撲と同様に痛み、腫れ、内出血などが起こりますが、より深部の組織(筋肉の深い部分、骨など)が損傷している可能性も含まれます。例えば、「筋挫傷(肉離れとは異なる、筋肉への強い打撃による損傷)」や「骨挫傷(骨の内部での内出血)」などがこれにあたります。
特徴: 打撲よりも損傷の範囲や深さが大きい場合に使われることがあります。特に、深部の重要な臓器や骨に損傷が及ぶ可能性も考慮されます。皮膚が断裂して傷口が開いている場合は「挫創(ざそう)」として区別されます。
3. 血腫(けっしゅ)
定義: 内出血によって、体内の組織内に血液が溜まって塊(こぶ)のようになった状態を指します。
症状: 腫れ、痛み、皮膚の変色(青あざから黒、緑、黄色へと変化)などがみられます。
特徴: 打撲や挫傷の結果として生じることが多いです。血液が溜まる場所によって、「皮下血腫(皮膚の下にできるもの)」、「脳硬膜下血腫(脳を覆う膜の下にできるもの)」、「耳血腫(耳にできるもの)」など、様々な種類があります。血腫が大きくなると、周囲の組織を圧迫して症状を引き起こすことがあります。
まとめると
打撲は、外からの衝撃によって皮下組織や筋肉などが損傷する、比較的軽い非開放性損傷(外に傷がない)の総称。
挫傷は、打撲よりも広義で、鈍的な外力による体内の組織や臓器の損傷全般を指します。打撲は挫傷の一種とも言えますが、より深部の損傷も含まれる場合があります。
血腫は、打撲や挫傷の結果として、体内に血液が溜まってできた塊のことです。
交通事故の7割弱が打撲
交通事故と聞くと、骨折や意識不明といった重篤な怪我を想像しがちです。しかし、実は交通事故で最も多く見られる損傷は「打撲」であり、その割合は全体の約7割にものぼると言われています。
打撲が多発する理由
なぜ交通事故で打撲が多いのでしょうか。
衝突時の衝撃: 車同士の衝突や、歩行者と車両の接触など、交通事故では瞬間的に大きな衝撃が体に加わります。この衝撃が直接、体の一部に集中することで打撲が生じます。
シートベルトの締め付け: 安全のために着用するシートベルトも、衝突時には体をしっかりと固定することで、内臓の損傷などを防ぎます。しかし、その締め付けが原因で、シートベルトが当たっていた部分に打撲を負うことがあります。
体勢の急変: 衝突によって体が予期せぬ方向に投げ出されたり、車内で何かにぶつかったりすることで、全身に打撲を負うケースも少なくありません。
「打ち身」とあなどれない打撲
打撲とは、身体が外部からの衝撃を受けることで、皮膚表面には傷がないものの、皮下組織や筋肉、血管などが損傷を受ける状態を指します。皮膚表面の傷がなく、血液を直接見ることがないため、軽視してしまいがちですが、衝撃の大きさによっては、重大な症状を引き起こすことがあるので注意が必要です。
打撲の症状
「ただの打ち身だから」と自己判断してしまうと、後になって症状が悪化したり、慢性的な痛みに悩まされたりするケースもあります。交通事故後の打撲で注意すべき症状としては、以下のようなものが挙げられます。
痛み: 患部にズキズキとした痛みや鈍痛を感じます。筋肉・神経・骨といった組織損傷が起きているために生じます。
腫れ: 衝撃を受けた部分が腫れ上がることがあります。血管損傷により、その部分に血液が漏れ出て腫れあがります。
内出血(青あざ): 血管が損傷し、血液が漏れ出すことで皮膚の下に青や紫色のあざができます。
熱感: 患部が熱を持つことがあります。損傷部を修復する過程において、組織が熱を持ちます。損傷の度合いが大きいほど熱は高くなります。
機能障害: 痛みが強いために、関節の可動域が制限されたり、筋肉を動かしにくくなったりすることがあります。怪我の初期段階では痛みのために動かせないのが普通ですが、4~5日が経過して痛みが低下してもなお動かせない場合、神経、筋肉、関節部の損傷などの可能性も考慮されます。
軽度でも医療機関の受診を
交通事故に遭った際は、たとえ目に見える外傷がなくても、必ず医療機関を受診することが重要です。特に交通事故での打撲は、骨折や内部損傷を伴っていることもあります。適切な診断を受けることで、症状に応じた治療を開始し、後遺症のリスクを最小限に抑えることができます。
交通事故後の打撲は、決して軽視できるものではありません。
自損事故や遠地での交通事故であったため、病院に行かなかったという方もいると思います。
その場合、ご自身で体の異変に注意しなければなりません。もし症状の悪化などを少しでも感じ場合は、すぐに専門家の診察を受け、早期の回復を目指しましょう。
症状に不安のある方は「こはた接骨院」へご相談ください >>>
交通事故での打撲:多い負傷部位と注意点
交通事故に遭遇した際、目に見える大きな外傷がなくても、体には相当な衝撃が加わっています。特に「打撲」は、交通事故で最も多く見られる怪我の一つであり、その負傷部位は多岐にわたります。
交通事故で打撲を負いやすい部位は、次の順で多くみられます。1)
1.頭部
2.顔面
3.下肢
4.頸部
5.上腹部
6.上肢
7.下腹部
それぞれの部位における注意点について解説します。
1. 頭部
交通事故では、ハンドルやダッシュボード、窓ガラス、または地面などに頭を打ち付けることで、打撲を負う可能性が非常に高い部位です。
注意点: 頭部の打撲は、脳震盪や頭蓋内出血など、目に見えない重篤な損傷を伴う可能性があります。意識の混濁、吐き気、嘔吐、めまい、頭痛の悪化、視覚異常、手足のしびれ、呂律が回らないなどの症状が見られる場合は、直ちに救急車を呼ぶか、緊急で医療機関を受診してください。症状がなくても、念のため頭部のCT検査などを推奨します。
精密検査を受けておくことで、後々症状が出たときに、交通事故によるものかを判断するうえでも重要な資料になります。
2. 顔面
衝突の際、顔がハンドルやエアバッグ、フロントガラスなどに当たることで、顔面の打撲はよく発生します。
注意点: 顔面は骨が薄く、複雑な構造をしているため、軽微な打撲によって骨折(鼻骨骨折、眼窩底骨折など)を伴うことがあります。また、視力や嗅覚、味覚、聴覚といった感覚器に影響が出たり、口の動きや顔の表情に麻痺が生じたりする可能性もあります。内出血が広がりやすく、美容的な問題にもつながるため、腫れや痛みが強い場合は、眼科、耳鼻咽喉科、口腔外科などの診療科目をまたいでの診察も検討しましょう。
3. 下肢(脚、足)
フットレストやペダルへの衝突、歩行者の場合は車両との接触などで、下肢の打撲は頻繁に起こります。
注意点: 膝や脛、足首など、衝撃を受けやすい部位が多く、骨折や靭帯損傷、半月板損傷など、重い損傷を併発することがあります。特に、腫れがひどい場合や、体重をかけると激痛が走る場合は、骨折の可能性を疑い、整形外科を受診してください。血腫が大きくなると、コンパートメント症候群(筋肉内の圧力が高まり、神経や血管を圧迫する状態)を引き起こし、痛みが長引くこともあるため注意が必要です。
4. 頸部(首)
追突事故で最も特徴的なのが、この頸部の打撲です。「むちうち」と表現されることも多いですが、これは頸部の軟部組織(筋肉、靭帯など)が過伸展・過屈曲によって損傷する打撲の一種です。
注意点: 事故直後には症状が出なくても、数時間から数日経ってから痛みや可動域制限、しびれ、めまい、頭痛などの症状が現れることがあります。放置すると慢性的な痛みに移行するリスクがあるため、事故後は症状がなくてもできるだけ早く整形外科を受診し、レントゲンやMRIなどで異常がないか確認することが重要です。
5. 上腹部(胸部、みぞおち周辺)
シートベルトによる締め付けや、ハンドルへの衝突などで、上腹部に打撲を負うことがあります。
注意点: 外見上は単なる打撲に見えても、肋骨骨折や内臓(肺、心臓、肝臓、脾臓など)の損傷を伴う可能性があります。息苦しさ、咳、胸の強い痛み、腹部の圧痛、冷や汗、意識の混濁などが見られる場合は、緊急性が高いため、速やかに医療機関を受診してください。特にシートベルト跡が強く残っている場合は注意が必要です。
6. 上肢(腕、手)
ハンドルを握っていた手や腕、体を支えようとした際に、上肢をダッシュボードやドアなどにぶつけることで打撲が生じます。
注意点: 肩、肘、手首、指など、関節の多い部位は、打撲によって関節の可動域制限や靭帯損傷、骨折を伴うことがあります。特に、腫れや痛みが強い場合、変形が見られる場合は、骨折の可能性を疑い、整形外科での診察が必要です。手先や指のしびれがある場合は、神経損傷も考慮されます。
7. 下腹部(骨盤周辺)
シートベルトの締め付けや、衝突の際に体が強く前に押し出されることで、下腹部や骨盤周辺に打撲を負うことがあります。
注意点: 骨盤骨折や膀胱、腸などの泌尿生殖器系、消化器系の内臓損傷の可能性があります。排尿時の痛みや血尿、下腹部の強い痛み、便秘や下痢などの症状がある場合は、泌尿器科や消化器内科、または総合病院での精密検査が必要です。女性の場合は、婦人科系の問題に発展する可能性も考慮されます。
交通事故に遭ってしまったら、たとえ痛みが軽くても、また目に見える傷がなくても、「大したことはないだろう」と自己判断せず、必ず医療機関を受診してください。早期に適切な診断と治療を受けることが、後遺症を防ぎ、早期回復への一番の近道となります。
交通事故の種類別:負傷しやすい部位と身を守る予防策
交通事故は、その種類によって負傷しやすい部位や怪我の程度が大きく異なります。ご自身がどのような状況で事故に遭遇する可能性があるかを理解し、適切な予防策を講じることが、いざという時の被害を最小限に抑える鍵となります。2)
1. 自転車や歩行者の事故:最も注意すべきは「頭部」
自転車に乗っている時や道を歩いている時に車と衝突した場合、非常に危険性が高いのが「頭部」への損傷です。体の中で最も重要な脳が収まっている頭部は、一度ダメージを受けると、命に関わったり、重い後遺症を残したりする可能性が高まります。
なぜ頭部が危ないのか?
自転車や歩行者は、車のように体を覆うものがありません。衝突の衝撃で直接地面に叩きつけられたり、車体に頭部をぶつけたりすることが多いため、脳に深刻なダメージを受ける「重篤な頭蓋内損傷」や、命の危険に瀕するほどの外傷につながりやすいのです。
自分でできる予防法・注意方法

ヘルメットの着用:
自転車に乗る際は、年齢や距離に関わらず必ずヘルメットを着用しましょう。万が一の転倒や衝突時に、頭部への衝撃を大きく軽減してくれます。安全基準を満たした、サイズの合ったものを選ぶことが重要です。

明るい服装・反射材の活用:
特に夜間や薄暗い時間帯は、ドライバーから見えにくくなります。明るい色の服を選び、反射材付きのグッズ(タスキ、リストバンド、靴など)を身につけることで、自分の存在をアピールし、事故のリスクを減らしましょう。

歩道や安全な場所の利用:
可能な限り歩道を利用し、車道に出る際は細心の注意を払いましょう。見通しの悪い場所や交通量の多い場所では、より一層の警戒が必要です。

信号や交通ルールの厳守:
「これくらいなら大丈夫だろう」という油断が事故につながります。信号は必ず守り、一時停止や横断歩道など、交通ルールを徹底することが自分を守る第一歩です。
2. 自動二輪車(バイク)の運転者:特に注意したい「顔面」と「胸部」
バイクは四輪車に比べて体がむき出しになるため、事故の際の負傷リスクが高まります。特に、顔面や胸部に深刻なダメージを受けるケースが多く見られます。
なぜ顔面・胸部が危ないのか?
衝突時に、体ごと投げ出されたり、ハンドルや車体に顔や胸が強く打ち付けられたりすることが多いためです。顔面は衝撃に弱く、胸部には心臓や肺といった生命維持に不可欠な臓器が集中しているため、重症化しやすい傾向があります。
自分でできる予防法・注意方法

フルフェイスヘルメットの着用:
顔面保護のためには、あごまで覆うフルフェイスヘルメットの着用が必須です。あご紐をしっかりと締め、サイズが合っているか確認しましょう。

プロテクターの着用:
胸部や背中、肩、肘、膝などを保護するプロテクターを着用することで、万が一の衝撃を吸収し、負傷のリスクを減らすことができます。

安全運転の徹底:
車線変更時の確認、無理なすり抜けをしない、スピードを出しすぎないなど、常に危険を予測した安全運転を心がけましょう。バイクは死角に入りやすいため、車のドライバーに自分の存在を知らせる意識も重要です。

視認性の向上:
明るい色のウェアや反射材を取り入れることで、他の車両からの視認性を高め、事故の予防につなげましょう。
3. 四輪車(自動車)の運転者や助手席の同乗者:意外と多い「胸部」や「腹部」の損傷
自動車に乗っている場合、比較的安全性が高いと思われがちですが、衝突時の衝撃は予想以上に大きく、特に胸部や腹部に軽症から重症まで様々な損傷が発生しやすいことが分かっています。頭部外傷の重症例は少ない傾向にありますが、これはシートベルトやエアバッグによる保護効果が大きいためと考えられます。
なぜ胸部・腹部が危ないのか?
衝突の瞬間、シートベルトが体を強く拘束することで、胸部や腹部に圧力がかかります。また、ハンドルやダッシュボードに体を打ち付けることで、胸骨骨折や肋骨骨折、さらには内臓(心臓、肺、肝臓、脾臓など)の損傷につながる可能性があります。
自分でできる予防法・注意方法

シートベルトの正しい着用:
肩ベルトが首にかからず、鎖骨と肩の間を通るように、腰ベルトが骨盤の低い位置を通るように正しく着用しましょう。たるみがないようにしっかりと締め、ねじれがないことも確認してください。これが最も基本的な、かつ効果的な予防策です。

適切な運転姿勢:
シートを適切に調整し、ハンドルとの距離を保ちましょう。エアバッグが適切に作動するためにも、適切な運転姿勢が重要です。
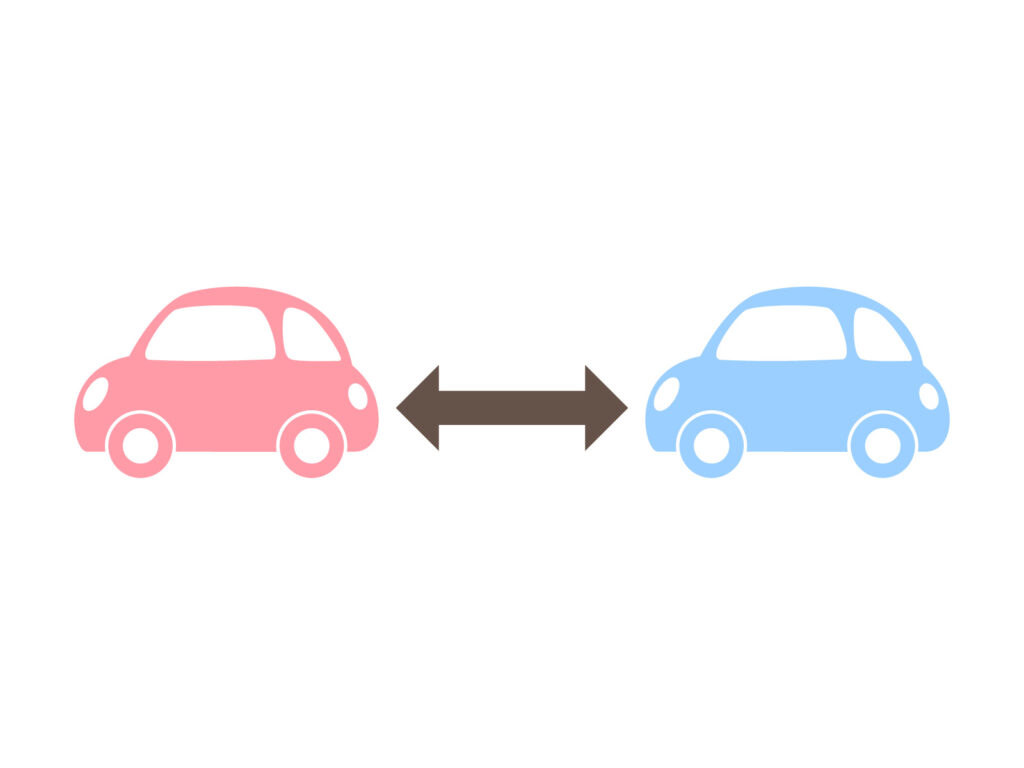
安全速度の厳守と車間距離の確保:
スピードを出しすぎないこと、そして十分な車間距離を保つことで、急ブレーキや衝突の際の衝撃を和らげる時間を稼ぐことができます。

居眠り運転・ながら運転の禁止:
疲労時や注意散漫な状態での運転は事故リスクを格段に高めます。休憩をしっかり取り、スマートフォンの操作などは絶対にやめましょう。
まとめ:もしもの時のために知っておくべきこと
交通事故は、いつ誰の身に起こるか予測できません。しかし、それぞれの状況で特にリスクが高い部位と、それに対する予防策を知り、日頃から実践することで、被害を最小限に抑えることは可能です。
万が一事故に遭ってしまった場合は、たとえ軽微な痛みでも、必ず医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けるようにしましょう。見た目では分からない体の内部の損傷がある場合も少なくありません。早期の対応が、後遺症を防ぎ、早期回復への鍵となります。
年齢層別に見る交通事故の傾向
交通事故の発生状況を分析すると、二つの年齢層に事事故が多く発生する傾向が見られます。2)
交通事故は、年齢層によって発生しやすい種類や状況が異なります。自身の年齢層でどのような事故が多いのかを知ることは、効果的な予防策を講じる上で非常に重要です。
四輪車(自動車)の事故
20歳代: 運転経験が浅いことや、行動範囲が広がることで事故のピークが見られます。
50歳代: 運転歴が長くなり、油断や身体能力のわずかな変化が影響してか、再び事故が増える傾向にあります。
自動二輪車(バイク)の事故
20歳代: 特にこの年代で事故が最も多く発生するピークが見られます。免許取得直後で経験が不足していたり、速度を出しすぎたりする傾向があることが考えられます。
自転車の事故
学童〜10歳代: 小学生から中高生にかけて、自転車を利用する機会が増え、交通ルールへの理解が不十分だったり、注意力散漫になりやすかったりすることから事故のピークがあります。
高齢者: 身体能力の低下(バランス感覚や視力・聴力など)や、危険察知能力の低下が影響し、再び事故が増える傾向が見られます。
歩行者の事故
学童: 交通量の多い場所での行動が増え、交通安全への意識がまだ十分に育っていないため、事故に遭いやすい傾向があります。
高齢者: 身体能力の低下に加え、交通状況の判断の遅れや、夜間の外出での視認性の低さなどが原因で、事故のリスクが高まります。
各年代が特に気をつけたいこと
これらのデータから、20歳代、50歳代、そして学童〜10歳代、高齢者は特に交通事故に遭う、または事故を起こして重症化するリスクが高い層であると言えます。
20歳代(四輪車・自動二輪車)の方へ
運転に慣れてきたと感じる時期かもしれませんが、過信は禁物です。速度超過や無理な割り込みはせず、常に安全運転を心がけましょう。特にバイクに乗る際は、ヘルメットやプロテクターを適切に着用し、自分の身を守る装備を怠らないでください。
50歳代(四輪車)の方へ
運転経験が豊富だからこそ、「慣れ」による油断に注意が必要です。加齢に伴う身体能力のわずかな変化(視力、聴力、反応速度など)を自覚し、定期的に運転適性診断を受けるなどして、安全な運転を維持しましょう。
学童〜10歳代(自転車・歩行者)の方へ
交通ルールをしっかりと守ることが何よりも重要です。自転車に乗る際はヘルメットを必ず着用し、夜間は反射材を身につけるなどして、自分の存在をドライバーにアピールしましょう。道路を渡る際は「止まって、見て、確かめる」を徹底してください。
高齢者(自転車・歩行者)の方へ
ご自身の身体能力の変化を認識し、無理のない行動を心がけましょう。自転車に乗ることが不安な場合は、公共交通機関の利用を検討したり、電動アシスト自転車の利用も視野に入れたりしてください。歩行時は、明るい服装や反射材を身につけ、暗い時間帯の外出はできるだけ避けるなど、ドライバーからの視認性を高める工夫をしましょう。また、横断歩道のない場所での横断は大変危険です。
交通事故は、いつ誰の身に起こるかわかりません。しかし、年代ごとの傾向を理解し、適切な安全対策と啓発活動を続けることで、そのリスクを減らすことができます。私たち一人ひとりが交通安全への意識を高め、注意を払うことが、悲しい事故をなくす第一歩となるでしょう。
交通事故で重傷にならないための対策:命を守るためにできること
交通事故はいつ誰の身にも起こりうるものですが、適切な対策を講じることで、万が一の際の重傷化リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、交通事故で重傷にならないための具体的な対策を分かりやすくご紹介します。
1. ヘルメットの着用を徹底し、その効果を最大限に
交通事故で最も重篤な損傷につながりやすいのが頭部外傷です。特に自転車や自動二輪車の事故では、頭部を守るヘルメットが命綱となります。
徹底すべきこと:
自転車に乗る際は必ずヘルメットを着用しましょう。お子さんだけでなく、大人も例外ではありません。
自動二輪車の運転者には、顔面までしっかり保護できるフルフェイス型ヘルメットの着用を強く推奨します。
高齢者や子どもへのヘルメット普及をさらに進めるための啓発活動も重要です。
ヘルメットは、ただかぶるだけでなく、あご紐をしっかり締め、グラグラしないサイズのものを選ぶことが大切です。
2. 車両側の安全装置を最大限に活用する
車両に搭載されている安全装置は、衝突時の衝撃から私たちを守るためのものです。これらの技術を最大限に活用し、さらにその普及を進めることが重傷化を防ぐ鍵となります。
自動車の場合:
サイドエアバッグや、衝突時の衝撃を吸収する強化された車体構造を持つ車両を選びましょう。
最新の安全技術(衝突被害軽減ブレーキなど)が搭載された車両も、事故自体を防ぐ上で非常に有効です。
自動二輪車(バイク)の場合:
胸部プロテクターや、万が一の際に膨らんで体を保護するエアバッグ搭載ライダースーツの着用を積極的に検討しましょう。これらは胸部や腹部の重篤な損傷を防ぐ上で大きな効果を発揮します。
3. 歩行者・自転車のための安全な道路環境を整備する
歩行者や自転車利用者が安全に通行できる道路環境を整えることは、事故そのものを減らすための根本的な対策です。
安全な道路の利用:
歩道や自転車専用道の整備・拡充が不可欠です。車道と歩行者・自転車が明確に分離されることで、車両との接触や衝突のリスクが大幅に低減されます。
これらの整備が進んだ場所を積極的に利用しましょう。
4. 交通ルールを徹底し、違反をなくす
どんなに安全装置が進化しても、交通ルールが守られなければ事故は防げません。交通ルールを遵守し、危険な運転行動をなくすことが、事故の発生頻度自体を減らす最も直接的な対策です。
ドライバーの皆さんへ:
スピードを出しすぎない、一時停止を守る、信号無視をしないなど、基本的な交通ルールを再確認し、常に徹底しましょう。
飲酒運転やながら運転は絶対にやめましょう。
歩行者・自転車の皆さんへ:
信号を守り、横断歩道を渡りましょう。
自転車も車両の一種であることを認識し、交通ルールを遵守しましょう。
取り締まりの強化:
警察による交通違反の取り締まり強化も、安全意識の向上につながります。
5. 高齢者と子どもの交通安全教育を充実させる
交通事故の被害に遭いやすい学童期の子どもたちと、身体能力の変化に伴いリスクが高まる高齢者への安全対策は特に重要です。
子どもたちへ:
学校や地域で、交通安全教育を継続的に行い、危険予測能力を高める指導をしましょう。
保護者も一緒に、実際に道路を歩きながら安全な横断方法などを教えることが大切です。
高齢者の方へ:
加齢に伴う身体能力の変化(視力、聴力、反応速度など)を自覚し、交通状況の判断能力を維持・向上させるための啓発活動や講習に参加しましょう。
反射材付きの服装や明るい色の服を着用し、夜間の外出時は特に注意しましょう。
6. シートベルトと正しい座席姿勢を習慣にする
四輪車の事故で胸部や腹部の損傷を防ぐには、シートベルトの正しい着用が不可欠です。
常に徹底すべきこと:
全席でのシートベルト着用を義務付け、出発前には必ず全員が正しく着用しているか確認しましょう。
シートベルトがねじれていたり、緩んでいたりしないかチェックしましょう。
適切な座席姿勢を保ちましょう。背もたれを倒しすぎたり、極端に前傾姿勢になったりすると、シートベルトの効果が十分に発揮されず、体がシートベルトの下をすり抜ける「サブマリン現象」で内臓などを損傷するリスクが高まります。
交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても、人生を大きく左右する出来事です。今回ご紹介した対策は、いずれも私たち一人ひとりが日頃から意識し、実践できることばかりです。これらの対策を徹底することで、あなた自身だけでなく、大切な家族や友人の命を守ることにもつながります。
今一度、ご自身の交通安全意識と行動を見直してみませんか?
最後に
交通事故により打撲を生じたときの注意点、対処法を紹介しましたが、できれば、交通事故に遭わないこと、遭っても怪我を最小限にする予防を、普段から心がけましょう。
参考文献
1)加来信雄.国際交通安全学会誌.交通事故損傷とその対処の留意点.2000年1月.https://www.iatss.or.jp/entry_img/25-2-06.pdf,(参照 2025-07-07).
2)田中啓司.交通事故類型別にみた損傷部位と重症度の特徴-日本外傷データバンク2004-2008による検討-.日外傷会誌.26巻1号(2012).https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjast/26/1/26_26.1_01/_pdf,(参照 2025-07-07).